みなさんこんにちは、夏みかんです!
今回は絶対に序盤にやるべきであった日本文学の主要作品について流れを見ていきましょう。
中学校や高校ではこれらの作品を授業にて扱うことが多いと思うので、お役に立てればと思います!
それではさっそく行きましょう!!

どれも重要な作品だから時代の流れを覚えていこう!
そもそもどのような作品を学ぶのか
基本的に学校では、今後の記事で解説しますが入試での古文を読めるようによく使われるフレーズや動詞・形容詞・助詞などが含まれているもの、歴史的に重要なものを学びます。
古文に関しては今とは言葉遣いや文章のルールが大きく異なっている点が多いので、どの科目にも基本的に同じですが、やはり多くの作品を学習して身につけることが大事です。
これらの学習を通して、入試の際に初めて見る文章でも読めるように訓練をしていきます。
多くの作品を勉強していくのでもちろんジャンルも多々あり、そのことを知ることで作品への理解を深めることも大切です。ジャンルに関しては、「物語・説話・軍記・日記・随筆・和歌」などがあります。
それらについては以下で解説をしていきます。
物語
古文における物語とは、基本的に文字で書かれた読み物のことを言います。
一部では人々の間で話されていたものが含まれます。

例 『竹取物語』『伊勢物語』『源氏物語』
説話
説話は人々の間で広まっていった神話や伝説を指します。
これらの内容は自然と人々の暮らしの様相や宗教に関して書かれていることが多いです。
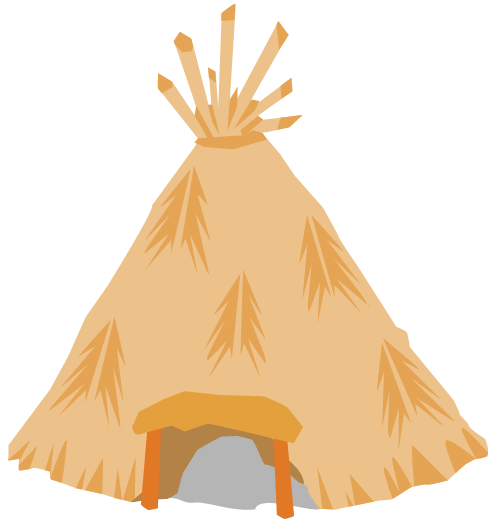
例 『今昔物語集』『宇治拾遺物語』
軍記
これは歴史上の戦を書き、そこにまつわる話も描写しているというものです。
これらが生まれた時代の多くは平安・鎌倉・室町という武士たちの活躍する時代です。

例 『将門記』『平家物語』
随筆
作者の経験や思いなどを想うがままに書いたものを随筆といいます。
近いものとしては、起源は異なりますが「エッセイ」があります。

例 『枕草子』『方丈記』『徒然草』
日記
日記は備忘録として貴族が書いていたものです。
元は漢文で書かれていましたが、仮名文字が生まれていくと文学の一つとなりました。

例 『土佐日記』『蜻蛉日記』
和歌
和歌とは「5・7・5・7・7」が一般的に基本となる歌のことです。
もともとは様々な種類がありましたが、上記のスタイルが主体になっていきました。
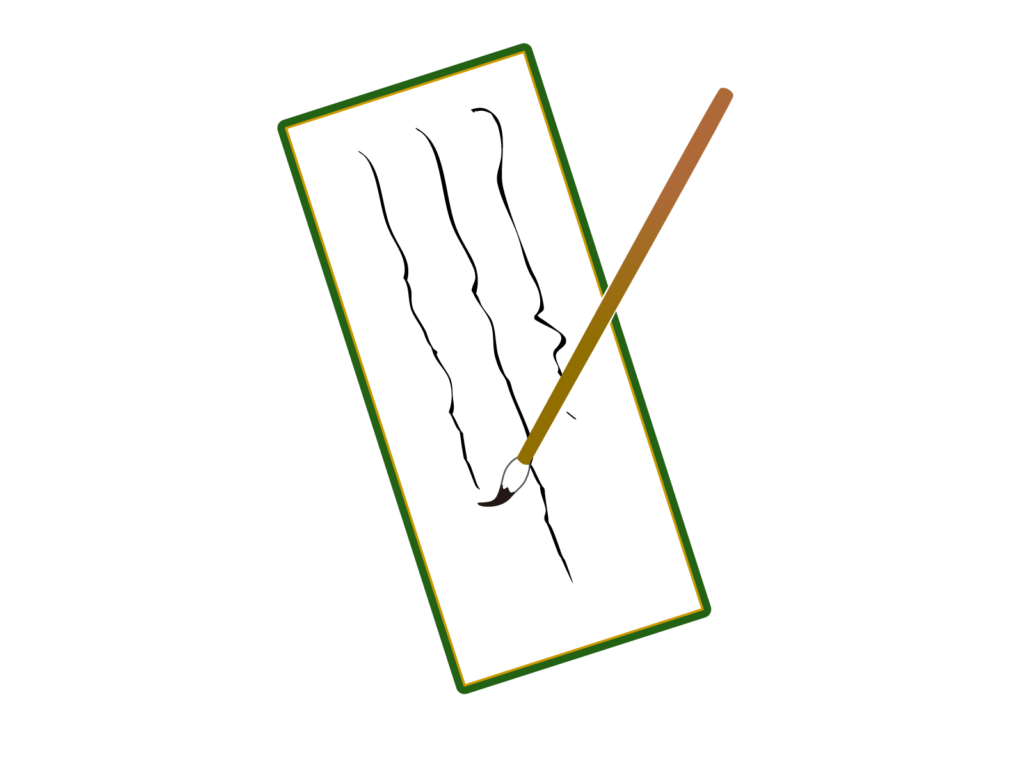
例 『古今和歌集』『新古今和歌集』
授業で扱う主要作品年鑑
では主にどのような作品を学習するのか見ていきましょう。
中学高校の古文の授業では主にこれら上記の作品を勉強することが多いです。
もちろんここに記載していないものを勉強することもあります。私が当時高校生だった際には『宇治拾遺物語』の「児のそら寝」というものを初回の授業で学びました。
古文というものは学べば学ぶほど読む力もついていくので、自分の好きな作品を見つけて知識をつけていきましょう!
まとめ
今回は中学高校にて学ぶことになるであろう古文の主要作品について軽くまとめてみました!
画像で紹介した作品たちは今後しっかりと解説をしていくので是非ご覧ください!

色々書いていくからよかったら見てね~!
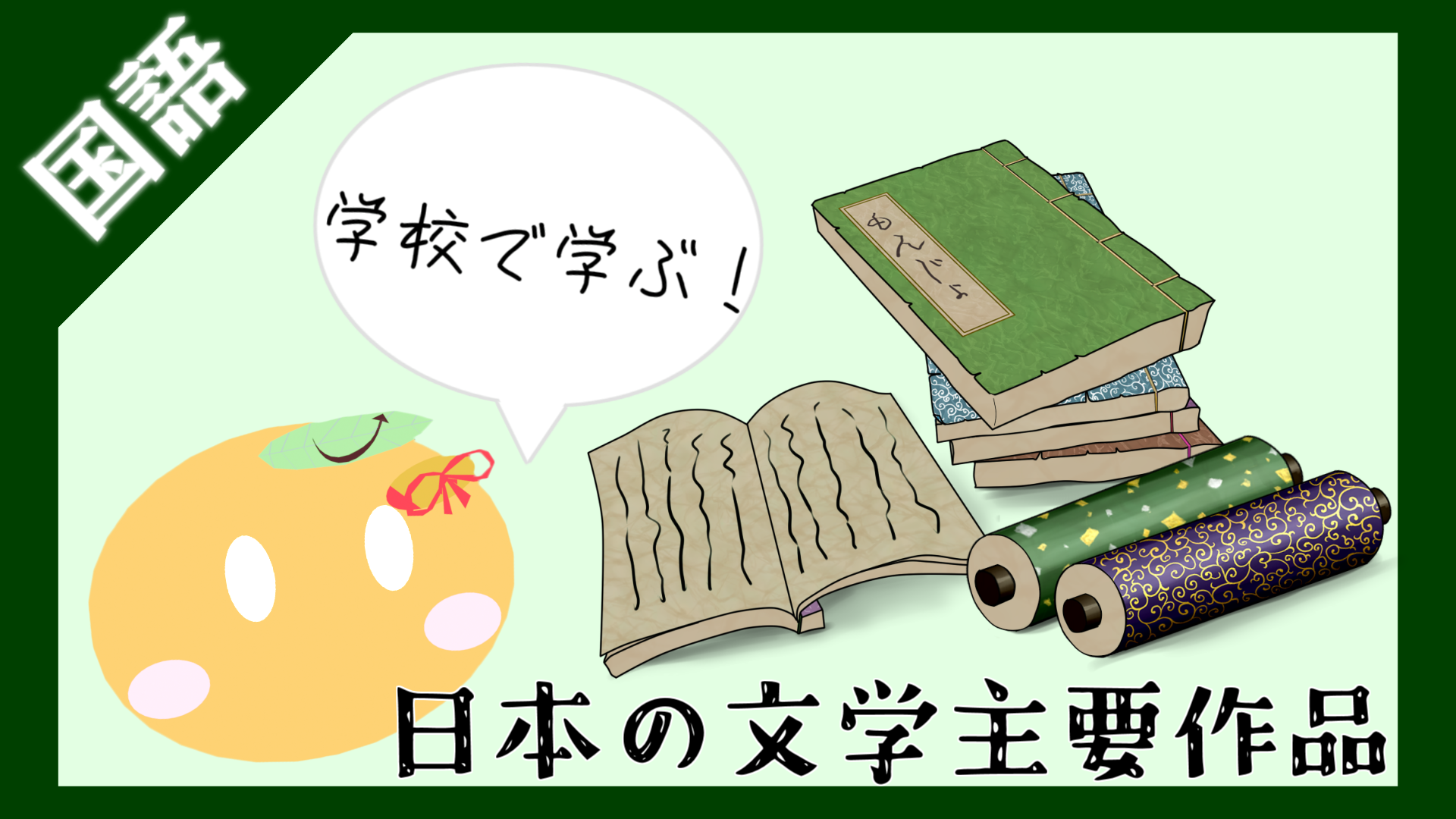


コメント